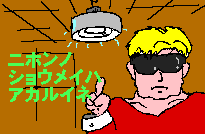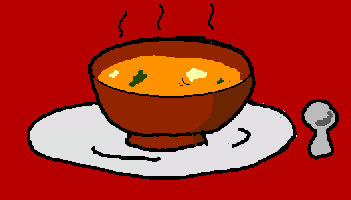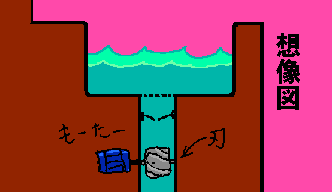アメリカ体験記・生活編
● "2"を表現するときは気をつけて(2001/05/05)
 TVでも時々とりあげられているが、欧米、特にヨーロッパでは、人差し指と中指だけを立て、その手の甲を相手に向けるのはやめた方がいい。
実はこの行為は中指を立てて「ファック・ユー!」と叫ぶあの行為に匹敵する。
(そういえば英国ドラマのレッド・ドワーフでも主人公がやっていたなあ)
TVでも時々とりあげられているが、欧米、特にヨーロッパでは、人差し指と中指だけを立て、その手の甲を相手に向けるのはやめた方がいい。
実はこの行為は中指を立てて「ファック・ユー!」と叫ぶあの行為に匹敵する。
(そういえば英国ドラマのレッド・ドワーフでも主人公がやっていたなあ)
なぜそうなるのか正確な説は不明だが私が聞いたところではその昔、敵を捕まえたときに二度と弓を引けないようにその2本の指を切断したそうな。
そこでその2本の指を相手に見せつけることで
「俺にはまだ弓を引くための2本の指があるんだぞ!おまえを射ぬいてやる!」
という意味になり、現在に至っているらしい。
実際には手の甲を相手に向けて人差し指と中指だけを立てても、
よほどにらみつけて手を突き出したりしない限りは勘違いされないと思うが、
こっちの習慣を理解していない日本人だと思われたり、万が一のトラブルに巻き込まれないとも限らないので注意しよう。
● 今までを振り返って(2001/04/03)
こうして振り返ってみると、アメリカも日本もいろいろ変わったと思う。
コーヒー関連も、いまでは「シアトル系」なるコーヒーショップが繁盛し、
ガソリンもかなり値上がりしているらしい。
日本でもパソコンの電源を昔ほどこまめに切らなくなったと思うし、
未成年に対する酒やたばこの販売規制がより厳しくなってきた。
日本もたばこの自販機がなくなる日がくるのだろうか。(ちなみに私は吸いません)
● たのむから酒をのませてくれ! (99/6/27)
 さあ、今夜は食事でもしながら酒を飲もうとレストランで注文すると、身分証明書を見せろと言われた。アメリカでは日本人は特に「年齢不詳」に見えるので、酒が飲める年齢かどうか確認してくるのだ。ああ、面倒くさい。日本ではそんなことは聞かれもしないのに...。
とりあえずそこではパスポートを提示すれば納得してくれた。他の店でも大抵はこれでなんとかなった(でもいちいち面倒だぞ!)。しかし、場所によってはそれでも「だめだ」と言う店もある。アメリカのこの州が発行した証明書を見せろというのだ。ええい、旅行者がそんなもんもっているかぁ!!!健闘もむなしく結局そこでは飲めずじまい(オヨヨ)。
さあ、今夜は食事でもしながら酒を飲もうとレストランで注文すると、身分証明書を見せろと言われた。アメリカでは日本人は特に「年齢不詳」に見えるので、酒が飲める年齢かどうか確認してくるのだ。ああ、面倒くさい。日本ではそんなことは聞かれもしないのに...。
とりあえずそこではパスポートを提示すれば納得してくれた。他の店でも大抵はこれでなんとかなった(でもいちいち面倒だぞ!)。しかし、場所によってはそれでも「だめだ」と言う店もある。アメリカのこの州が発行した証明書を見せろというのだ。ええい、旅行者がそんなもんもっているかぁ!!!健闘もむなしく結局そこでは飲めずじまい(オヨヨ)。
しかし、なぜにここまで厳しいのだろうか。アメリカには童顔の大人はいないだろうか。
本当かどうかは知らないが、聞いたところでは未成年者に飲ませた場合、数日間の営業停止処分があるという。まるで食中毒騒ぎのレベルだ。たしかに営業停止処分は店にとって恐ろしいのはわからなくもないが...
でもパスポートは認めてほしいなあ。
● 愛称っていったい...
アメリカには(イギリスとかでもそうだけど)愛称とかいうものがある。
愛称っていうことはニックネームっていうことか?早い話が「あだ名」か?
それなら日本でもあるじゃあないか。
ところがアメリカではほとんど「愛称」の方が「通常の名前」として使われている。
言ってみれば、みんな「芸名」を持っていて、それをいつも使っているようなものだ。
たとえば、アメリカ滞在時の上司の名前は"Bill(ビル)"だったが(ちなみに名字はゲイツではない)これは愛称で、実際には"William(ウイリアム)"というのだそうだ。
さらに驚くことに、公式な場でもこの「愛称」が通用してしまう。
例を挙げればアメリカ大統領のビル・クリントン大統領。そう、本当はウイリアムなのにほとんどの報道機関は愛称である「ビル」を使っているのだ。
しかし、このウイリアムならビルというように、愛称の付け方にはある程度の法則があり、チャールズならチャーリー、トーマスならトムというよに語尾を変えたり略したりするのが通例。
他にロバートならボブ、そしてビルのように略した後で言いやすいようになまる場合がある。
(なかには全然共通点がわからない愛称もあったような気がするが...思い出せない。ゴメンナサイ)
うーむ。結局、愛称は「略称」ということ???
● 缶コーヒーがない!
 日本にあって、アメリカにないものといえば「缶コーヒー」。
もともと防犯の都合上、自動販売機が少ないので出会う確率が低い。
しかも会社で飲み放題のコーヒーをわざわざ缶で飲もうなどとは考えもしないようだ。じつはアメリカで一番ほしかったものは、米や味噌汁よりも缶コーヒーだったりする(^^;)。だが最近、あのネッスルが、ちゃんとアメリカ人向けに缶コーヒーらしき飲料を発売してくれた。
「らしき」というのは、よく成分を確認していないのと、バニラなどハーブ系の風味が強くて、ちょっと期待していた味と違うため。3種類の味があったので、是非アメリカにいった際は飲んでみよう!
日本にあって、アメリカにないものといえば「缶コーヒー」。
もともと防犯の都合上、自動販売機が少ないので出会う確率が低い。
しかも会社で飲み放題のコーヒーをわざわざ缶で飲もうなどとは考えもしないようだ。じつはアメリカで一番ほしかったものは、米や味噌汁よりも缶コーヒーだったりする(^^;)。だが最近、あのネッスルが、ちゃんとアメリカ人向けに缶コーヒーらしき飲料を発売してくれた。
「らしき」というのは、よく成分を確認していないのと、バニラなどハーブ系の風味が強くて、ちょっと期待していた味と違うため。3種類の味があったので、是非アメリカにいった際は飲んでみよう!
※写真は後日送ってもらったアメリカで売られている日本の(?)缶コーヒーとLiptonの紅茶。日本人街や韓国食材店があれば楽に手に入るらしい(うむ、なるへそ)。
● S−VHSテープはありません
エンターテインメント花盛りのアメリカだが、ビデオテープの規格に関してはかなり保守的だ。まずS−VHSテープは普通のお店では手に入らない(デッキを売っているのは見たことがあるので全然ないわけではない)。みんな入手のしやすさが第一で、映りの善し悪しは二の次にされてしまうようだ。
ほかにも90年代初めの頃、日本では「8mmビデオ」と「VHS−C」のどちらがビデオカメラの主流になるのかとしのぎを削っていた頃、アメリカではなんと、肩にのせる「フルサイズのVHSカメラ」が売れ筋だった(片隅に8mmビデオカメラが追いやられていた。もちろんいまではフルサイズは廃れている)。
しかし彼らから見れば、次から次へと小型化のために新規格を出し、小さくなることに商品価値を求める日本の方が不思議なのかもしれない。
そういえば最近、VHSテープでもS−VHSなみの記録ができるVHS ETとかいう規格ができた。「テープの値段の差もそんなにないのになぜいまさら」と不思議に思っていたが、どうやらこれはこういった状況のアメリカ向けの規格のようだ。
● エナジー・スターの真実
パソコンを使っていない時の消費電力を押さえようという考えはアメリカで「グリーン・コンピュータ」だの「エナジー・スター」だのと呼ばれて、一気に普及した。
一見、アメリカ人はとても環境によい考えを持っているように見えるが、これには理由がある。
実はほとんどのアメリカ人は仕事が終わって家に帰るときもパソコンの電源を切らないのだ。エナジー・スターなどなかった時代にそれを目のあたりにした私は理由を尋ねたが、「たいして電気代がかからないのであまり気にしていない」らしい。
しかし、これら省電力コンピュータが増えたとたん、企業経営者は光熱費がかなり削減できたと大喜びしたとか。結局、「帰るときには電源を切りましょう」という方向へ考えがむかなかったようだ。どおりでWindows95やMacOSなど起動に時間がかかるOSばかり作るわけだ...
● なぜに直接照明を嫌うのよ!?
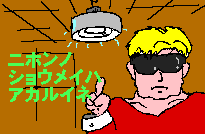
 アメリカの照明は、そのほとんどが間接照明。
使われているのも「電球」ばかりで「蛍光燈」はスーパーなどの広い場所や一部のオフィスを除き、ほとんど見かけることがない。
しかも、たまにみかける「蛍光燈」は直接「光」をみることがないようにと天井の「窪み」に取り付けられ、さらにその下に格子状の白い板がはめ込まれている(日本ではデパートの地下などでやってます)。そんなわけでアメリカの室内はどこへいってもちょっと暗め。昼間はそれでもいいのだが、夜に「本を読もう!」などと思うととても間接照明だけではつらい。
アメリカの人たちは毎晩、このホテルのようなランプ照明だけで暮らしているのだ。
電球文化は夜景がきれいなんだけど、夜型人間の私はちょっとついていけない。
しかし、なぜにここまで蛍光燈を嫌うのだろう?
「そういう文化だから。」と、言ってしまえばそれまでだが、以前、理由になりそうな情報を耳にした。なんでもコーカソイド(白人種といわれる人たち)の目が青いのは、その色素が薄いからで、他の人種より光を強く感じるのだそうだ。彼らがよくサングラスを使うのもそういった理由があるからで、カメラのフラッシュを使ったときにも比較的赤目になりやすいという。私は学者ではないので、実際の因果関係は断言できない(いろんな人種が住んでいる国ですし)が、少しは関係あるのでは...と思っている。
アメリカの照明は、そのほとんどが間接照明。
使われているのも「電球」ばかりで「蛍光燈」はスーパーなどの広い場所や一部のオフィスを除き、ほとんど見かけることがない。
しかも、たまにみかける「蛍光燈」は直接「光」をみることがないようにと天井の「窪み」に取り付けられ、さらにその下に格子状の白い板がはめ込まれている(日本ではデパートの地下などでやってます)。そんなわけでアメリカの室内はどこへいってもちょっと暗め。昼間はそれでもいいのだが、夜に「本を読もう!」などと思うととても間接照明だけではつらい。
アメリカの人たちは毎晩、このホテルのようなランプ照明だけで暮らしているのだ。
電球文化は夜景がきれいなんだけど、夜型人間の私はちょっとついていけない。
しかし、なぜにここまで蛍光燈を嫌うのだろう?
「そういう文化だから。」と、言ってしまえばそれまでだが、以前、理由になりそうな情報を耳にした。なんでもコーカソイド(白人種といわれる人たち)の目が青いのは、その色素が薄いからで、他の人種より光を強く感じるのだそうだ。彼らがよくサングラスを使うのもそういった理由があるからで、カメラのフラッシュを使ったときにも比較的赤目になりやすいという。私は学者ではないので、実際の因果関係は断言できない(いろんな人種が住んでいる国ですし)が、少しは関係あるのでは...と思っている。
● 傘をささない?アメリカ人
 私のいた地方では、車がないとちょっと不便なところだった。ある日、パラパラと雨が降り出したのだが、外の人たちは全く傘をさそうとしない。降りはどんどんひどくなるが、さそうとしない...というより、こんな日でも傘を持ち歩かないのだ。ここで日本人なら傘が無いときは少しでも濡れまいと走り出すものだが、その人たちは全然気にもせず普通に歩き続けている。
どうしたものかと知り合いに聞いてみると、「ここでは長く歩いても店と駐車場の間程度の距離だし、それくらいなら慌てても仕方がないからじゃないかな?」という答え。
まあ、レイン・コートの国だし、体に雨粒があたっても気にならないのかも。
私のいた地方では、車がないとちょっと不便なところだった。ある日、パラパラと雨が降り出したのだが、外の人たちは全く傘をさそうとしない。降りはどんどんひどくなるが、さそうとしない...というより、こんな日でも傘を持ち歩かないのだ。ここで日本人なら傘が無いときは少しでも濡れまいと走り出すものだが、その人たちは全然気にもせず普通に歩き続けている。
どうしたものかと知り合いに聞いてみると、「ここでは長く歩いても店と駐車場の間程度の距離だし、それくらいなら慌てても仕方がないからじゃないかな?」という答え。
まあ、レイン・コートの国だし、体に雨粒があたっても気にならないのかも。
しかし、アメリカはところ変われば習慣も変わる。サンフランシスコの都会では日本と同じように、みんなが傘をさしていたし、店先にも臨時の傘売場が現れる。
ここで売られている傘は「折り畳み傘」がほとんど。いわゆるビニール傘は少ない(やはり大きい傘を持って歩くのが嫌なのか?)。
だが、そこはアメリカ。折り畳み式でしかもワン・タッチ式(すごいぞ!)でありながら、値段は3ドルから5ドル程度とめちゃくちゃ安い(上の写真)。これは便利と、日本へ持って帰ったが...やはりアメリカ。2、3回使っただけでぼろぼろに...
● 自動ドアはみんな観音開き?
日本ではかなり普及している自動ドアだが、アメリカでは意外にすくない。
「先進国ならもっとたくさんあってもいいのに」と、ちょっと拍子抜け。
自動ドアがあるところと言えば、ホテルと空港ぐらい。あと大きなスーパーならあるかも。さらにそれらのドアのほとんどは観音開き式。日本のように、横に開くタイプはほとんど見かけない(たしかに引き戸の文化はアメリカにはないけど)。これでは一度出ようとしてまた戻ろうとしても遠回りしなくてはならないし、設置することを考えても出口用と入り口用のドアを二つ用意しなければならないわけで、とても不便だと思うのだが...。
ところで手動のドアもみんな観音開きなのだが、商店などの出入り口は必ず外側に開くようになっている。これは火事などのときにすぐに外に逃げられるように、法律で決まっているらしいのだ。もしかしたら自動のドアの事情もそういった法律に関係があるのかもしれない。
● お皿の上のお味噌汁
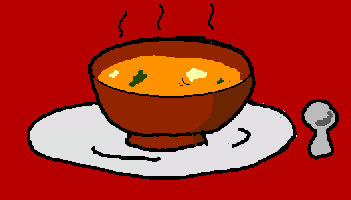 アメリカの大都市で日本食を食べるのに苦労したことはなかった。
しかし、ある郊外の中国料理店で「ミソ・スープ」を注文したのは間違いであった。
まず、一緒にいった人たちの頼んだコーンスープなどと一緒に、味噌汁も単品で先にでてきてしまった(そりゃあアメリカではスープから出すのが当然かもしれないけど、味噌汁っていえば、やっぱりご飯とおかずがあってだねぇ...以下略)。
しかも、お皿の上に味噌汁のお椀がのっていて、箸ではなく、スープ用スプーンが出てきたのである。こうまでされると、いったいどうやってこの味噌汁を飲もうか、日本人でありながら悩むハメになってしまった。結局、具はスプーンですくい、スープはお椀に直接口をつけて飲み干すことにした。意外と味のほうはちゃんとした味噌汁で、豆腐もしっかりしていて大変おいしかった。これだけちゃんとした味噌汁が作れるのにこのように扱われるとは...わざわざ外食で味噌汁を注文するのは現地人だけと考えるのも当然か?
アメリカの大都市で日本食を食べるのに苦労したことはなかった。
しかし、ある郊外の中国料理店で「ミソ・スープ」を注文したのは間違いであった。
まず、一緒にいった人たちの頼んだコーンスープなどと一緒に、味噌汁も単品で先にでてきてしまった(そりゃあアメリカではスープから出すのが当然かもしれないけど、味噌汁っていえば、やっぱりご飯とおかずがあってだねぇ...以下略)。
しかも、お皿の上に味噌汁のお椀がのっていて、箸ではなく、スープ用スプーンが出てきたのである。こうまでされると、いったいどうやってこの味噌汁を飲もうか、日本人でありながら悩むハメになってしまった。結局、具はスプーンですくい、スープはお椀に直接口をつけて飲み干すことにした。意外と味のほうはちゃんとした味噌汁で、豆腐もしっかりしていて大変おいしかった。これだけちゃんとした味噌汁が作れるのにこのように扱われるとは...わざわざ外食で味噌汁を注文するのは現地人だけと考えるのも当然か?
● 恐怖の排水口!?
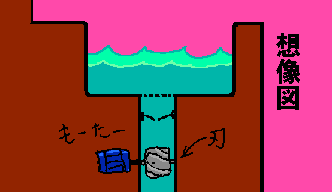 アメリカはリサイクル先進国と思われているが、そうなったのもここ十年ちょっとのこと。州や地域によって異なるが、家庭用のゴミ分別に関しては、むしろ東京よりずっと遅れているかもしれない。その代表ともいえるのが、流し台の排水口に埋め込まれた「生ゴミ粉砕カッター(仮名)」だ。野菜の切り残しなどをそのまま流し台に捨て、壁に付いているスイッチをオンにすると、ゴーッという轟音とともにそれらを細かく切り刻んで流すことができるという、まさに生ゴミ垂れ流し装置なのだ。まあ、下水処理場がちゃんと処理してくれればいいんだけど...。これは映画などでもよくでてくるので、知っている人も多いのでは。
アメリカはリサイクル先進国と思われているが、そうなったのもここ十年ちょっとのこと。州や地域によって異なるが、家庭用のゴミ分別に関しては、むしろ東京よりずっと遅れているかもしれない。その代表ともいえるのが、流し台の排水口に埋め込まれた「生ゴミ粉砕カッター(仮名)」だ。野菜の切り残しなどをそのまま流し台に捨て、壁に付いているスイッチをオンにすると、ゴーッという轟音とともにそれらを細かく切り刻んで流すことができるという、まさに生ゴミ垂れ流し装置なのだ。まあ、下水処理場がちゃんと処理してくれればいいんだけど...。これは映画などでもよくでてくるので、知っている人も多いのでは。
このホームページに記載されている情報は正式な裏付けを取ったものではありません。
これらの情報に間違いがあった場合でも当方では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
タイトル横の日付はこのページを更新した日時です。現地での体験日時ではありません。
TOPに戻る